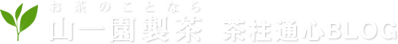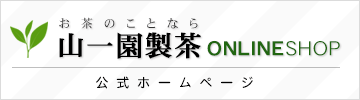はじめに
日本茶の世界で「棒茶(茎茶)」は、独特の香りとまろやかな味わいが魅力のお茶です。特に静岡と加賀(石川県)では、同じ棒茶と呼ばれても、それぞれ異なる製法によって、違う味・香り・水色の棒茶が誕生しました。それによって特徴が際立つ、ふたつの棒茶の楽しみ方が広がってきました。
本記事では、信頼できる情報源をもとに棒茶の歴史を紐解き、地域ごとの特徴と、山一園製茶ならではのこだわりをご紹介します。
棒茶とは?
棒茶は、茶葉の茎や葉脈部分を主原料としたお茶で、「茎茶」「かりがね」「雁ヶ音」などとも呼ばれます。
茎部分には旨味成分であるテアニンが豊富に含まれ、煎茶とは違う、まろはかな甘みがあります。また花の香り成分であるゲラニオールやリナロールも茶葉よりも多く含まれていて、芳醇な香りが特徴。熱湯でも渋みや苦味が出にくく、初心者から茶通まで幅広い層に好まれます。
主な特徴
-
甘みと軽やかな香り
-
熱湯でも美味しく淹れられる
-
食事や和菓子との相性が良い
棒茶の歴史
茎部分の利用から生まれたお茶
全国茶商工業協同組合連合会や茶問屋の解説によれば、棒茶(茎茶)は玉露や煎茶の仕上げ加工工程で選別された茎部分を活用して作られます。
手摘みでは、茶葉だけを摘むので、棒茶の原料はありません。明治時代以降、今と同じようなお茶の作り方が完成しました。
機械で摘むと茎の部部分も摘採されます。茶葉の生産量が増えてきたと同時に、茎の部分(棒茶の原料)も多くなりました。そしてお茶を機械で加工する技術もさかんに発明されて、茶葉と茎の選別技術も進んできました。
当時は煎茶がメインであり、茎は出物と呼ばれ、副産物としての位置づけでした。そこで、リーズナブルに仕入れられる茎を集め、棒茶に仕上げ販路を拡大していきました。
ここでのポイントは、茎を炒らず緑茶のカテゴリーとてして棒茶を販売いたことです。(現在では茎を炒って、棒ほうじ茶として販売も広く行われています)この後記載する加賀棒茶との大きな違いです。
加賀棒茶の歴史についてですが、まず加賀(石川県)とお茶のことをお話します。江戸時代、加賀藩の三代藩主前田利常が小松城に隠居後、裏千家の始祖である千仙叟室を招いて、茶道文化の発展に寄与しました。
また、加賀藩内に茶樹植栽を奨励、明治期には石川県は全国でも有数な茶葉の生産地とりました。幕末には輸出がさかんになり、明治期には国内生産の8割が海外に輸出されたそうです。そのため、庶民にとってお茶は高価なものとなりました。
そこで明治35年、金沢の茶商・林屋新兵衛が、副産物の茎部分の有効利用方法を開発。茎を焙じて炒った「加賀棒茶」を販売したところ、独特の香りと味わいで、人気となりました。
静岡棒茶との違いは、最初から茎を炒って販売したところです。
静岡の棒茶(山一園製茶)
特徴
静岡県全体の棒茶製法は多様ですが、山一園製茶では特に「香りと新鮮さ」を活かすため、あまり強い火入れをしないよう心がけています。
火入れを強くすれば保存性は高まりますが、お茶本来の香りや鮮度が損なわれるため、必要最低限にとどめています。
賞味期限へのこだわり
一般的なお茶屋では賞味期限を1年とすることが多い中、山一園製茶では半年に設定。
これは「お茶本来の香りと新鮮さを楽しんでいただきたい」という想いからであり、長期保存よりも風味の質を優先しています。
味わい
-
まろやか甘みと爽やかな香りが調和
-
おもてなしの一杯にも最適
-
淹れた瞬間に広がる新鮮な香り
加賀(石川県)の棒茶
特徴
加賀の棒茶は、茎を強く焙じる製法です。深い香ばしさと軽やかな後味が特徴で、焙じ茶に近い印象を持つ方も多いでしょう。
ブランド化
「加賀棒茶」という名称は全国に広まり、百貨店や観光土産として高い知名度を誇ります。香ばしい香りと淡い色合いが、他地域の棒茶と一線を画します。
味わい
-
香ばしさが強く、後味は軽やか
-
冷茶でも香りがしっかり立つ
-
贈答品としても人気
静岡と加賀の比較
| 項目 | 静岡の棒茶(山一園製茶) | 加賀の棒茶 |
|---|---|---|
| 焙煎 | 必要最低限(お茶本来の香り重視) | 強め(香ばしさ重視) |
| 味わい | 甘み・爽やか | 香ばしさ・軽やか |
| 用途 | 日常使い・おもてなし | 贈答・観光土産 |
棒茶の楽しみ方
-
淹れ方:熱湯でさっと淹れると香りが引き立ちます。
-
飲み比べ:静岡と加賀の棒茶を同条件で淹れて比較すると違いがはっきり分かります。
-
ペアリング:和菓子や軽い洋菓子、あっさり料理と好相性。
山一園製茶のおすすめ棒茶
山一園製茶では、静岡県産の上質な茎を使用し、香りを最大限に生かした棒茶をご用意しています。
▶ 山一園製茶の棒茶商品一覧はこちら
まとめ
棒茶は、地域によって製法や香りが大きく異なります。静岡の棒茶はお茶本来の旨味、香りと鮮度、加賀の棒茶は香ばしさが魅力です。
歴史的背景や製法の違いを知ることで、より一層棒茶の味わいを楽しめるはずです。ぜひ飲み比べて、自分だけの「一番の棒茶」を見つけてください。
内部リンク候補
-
「棒茶の淹れ方完全ガイド」
-
「棒茶の健康効果」
-
「棒茶の保存方法と香りを守るコツ」